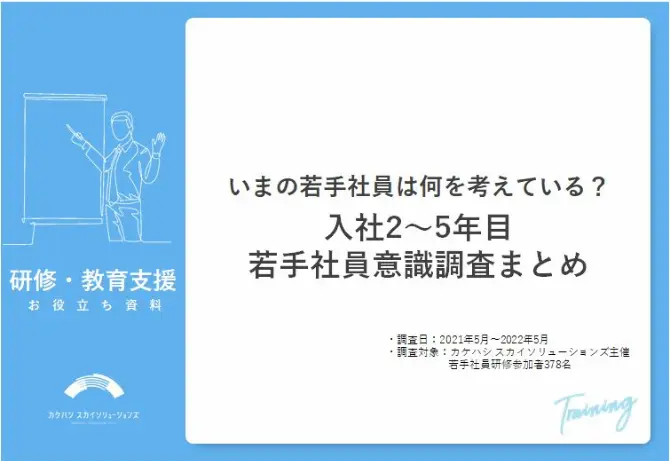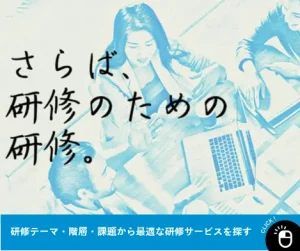少子高齢化により人手不足が深刻化する近年では、従業員の離職率は人事が把握すべき課題の一つです。
離職率の高い企業では、自社の抱える「問題」を見つけ出し改善するなど策を講じる必要があります。
この記事では、企業の「働きやすさ」の指標でもある離職率の計算方法についてと、計算する際に気をつけたい注意点、業界別の離職率の傾向などを紹介します。
目次
離職率・定着率の計算方法とは?
 離職率とは、企業に在籍している従業員のうち、一定期間に退職した人数の割合のことを指します。
離職率とは、企業に在籍している従業員のうち、一定期間に退職した人数の割合のことを指します。
一定の期間でどれだけの従業員が企業を退職しているのかがわかるため、企業の働きやすさの指標になるといわれています。
離職率の計算方法は、法律で定義されておらず企業によって異なります。厚生労働省が雇用動向調査で使用している計算方法は以下の通りです。
離職率=離職者数÷1月1日現在の常用労働者数×100
これに対して、一般的な企業の離職率には、以下の計算式が用いられることが多いです。
離職率=企業が定めた期間の離職者数÷起算日の在籍人数×100
期間も起算日も規定がないため、企業が独自に定めた期間と起算日で計算します。
例えば2年前に入社した新入社員の離職率を出したい場合、2年前の4月1日の在籍人数が100人、2年間で5人が退職したとすると離職率は5%となります。
この時、途中入社した人数は省きます。
この離職率とは反対に、入社した従業員が一定期間後にどのくらい残っているか(定着しているか)を示す指標に「定着率」があります。
定着率は以下のいずれかの計算式で算出できます。
1.定着率=100%-離職率
2.定着率=一定期間を経て残っている人数÷起算日の在籍人数×100
(参考:厚生労働省「雇用動向調査:調査の結果」)
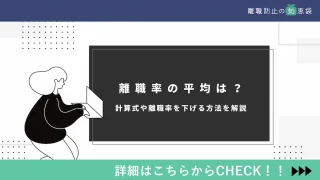
全従業員の離職率の計算例
全従業員の離職率を出したい場合、以下の計算式で算出できます。
離職率=離職人数÷従業員数×100
例えば、1月1日現在の常用労働者数が1000人の会社で、1年間で50名が離職した場合、上の計算式に当てはめると、「50÷1000×100=5」となり、その年の全従業員の離職率は5%となります。
新卒社員の離職率の計算例
新卒社員に限定して離職率を出す方法もあります。4月に採用した新卒者の1年後の離職率を出したい場合は、以下の計算式で算出可能です。
離職率=新卒社員の1年間での離職人数÷新卒社員数×100
4月に採用した新卒社員が20名いる会社で、翌3月までに4名が退職した場合の離職率は、「4÷20×100=20」で、20%となります。
3年後離職率の計算例
新卒採用の離職率の場合、3年後離職率の指標が重要ともいわれます。
一般的に3年以内の離職を「早期離職」と定義します。3年後離職率が低ければ働きやすい企業であると判断できることから、人事担当者が意識しなければならない数値です。
なぜ3年後が重要かというと、初めて就職した会社の離職理由が、1年未満の人と3年以上の人では変化するからです。
新卒社員が1年未満で退職した場合、「人間関係や労働条件がよくなかった」という理由が大半を占めます。一方で、3年以上勤務して退職した場合は、「結婚や子育てのため」や「将来性を考えて」といったようなライフプランに合わせた退職理由の割合が多くなるのです。
3年後離職率の計算方法は以下の計算式が当てはまります。
3年後離職率=〇〇年度に入社した新卒社員のうち、3年以内に離職した従業員数÷〇〇年度に入社した新卒社員数×100
例えば、2021年度に100人の新卒社員が入社し、2021~2023年度の間に30名が離職した場合、「30÷100×100=30」となり、2021年度の3年後離職率は30%と算出できます。
離職率を計算する際の注意点
 計算方法が法律で定義されていないため、実際に離職率を計算・比較する際に注意しなければならない点がいくつかあります。
計算方法が法律で定義されていないため、実際に離職率を計算・比較する際に注意しなければならない点がいくつかあります。
ここでは、大きく分けて二つの注意点を紹介します。
「一定期間」内に入社・退職した人が計算に含まれない
前述した一般的な計算方法の場合、離職率を計算する際に企業が決めた「一定期間」の間に入社して退職した従業員は離職率に含めません。
そのため、必ずしも正確な離職率を算出できないことを頭に入れておきましょう。
例えば、一定期間を2021年4月1日から2022年3月31日までとした場合、2021年4月2日に5人入社し、2022年3月30日に5人退職したとします。
すると、本来なら離職率は100%ですが、一定期間内のため計算には含まれず、離職率は0%となってしまうのです。
離職率は調整可能である
上述したように、離職率が100%では企業イメージが悪くなるため、離職率を計算する際の「一定期間」を意図的に調整することも容易です。
企業にとって都合のよい離職率ばかりを算出していては、根本的な問題解決にはつながりません。
自社の離職率は、離職率の軽減や入社率の向上を目的とした一つの指標であり、決して企業の印象をよく見せるために算出するわけではないことを頭に入れておきましょう。
どのくらいの離職率が問題ない水準とされるのか?
自社の離職率が低いのか高いのか、知りたい方も多いのではないでしょうか。
ここでは、2021年に実施された厚生労働省の雇用動向調査をもとに、日本企業の平均離職率を紹介しますので参考にしてください。
| 1月1日の常用 労働者数(千人) |
離職者数(千人) | 離職率(%) | |
| 一般労働者 | 37,140.60 | 4,129.90 | 11.1 |
| パートタイム労働者 | 14,318.10 | 3,042.70 | 21.3 |
| 合計 | 51,458.80 | 7,172.50 | 13.9 |
(参考:厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概況」)
日本企業の一般労働者・パートタイム労働者を合わせた平均離職率は13.9%です。
また、企業の働きやすさを判断する指標として重要視されている「3年後離職率」では、3割が一つの基準となります。
3割を上回っている離職率の高い企業の場合、今一度自社の従業員の働く環境に問題がないか調べてみた方がよいでしょう。
離職率の高い企業の特徴とは?
 離職率が高まりやすい企業には、共通する特徴がいくつかあります。組織が抱える課題を洗い出し、一つひとつの問題を解決していきましょう。
離職率が高まりやすい企業には、共通する特徴がいくつかあります。組織が抱える課題を洗い出し、一つひとつの問題を解決していきましょう。
特徴(1)評価が正しくおこなわれない
離職率が高い企業は、人事評価制度に問題を抱えていることがあります。評価基準の曖昧さや上司の個人的な感情による評価は、不公平感や不満を募らせる要因です。
そもそもどのような基準で評価がなされているかが公開されていない場合、社員は正しく評価されているのかの判断ができません。
「いくら頑張っても評価されない」と社員が感じている状態をそのままにしてしまうと、モチベーションの低下につながる恐れがあります。
特徴(2)業務量が多い・労働時間が長い
離職率が高い企業の特徴として、「業務量が多い」「拘束時間が長い」といったものもあります。これらは、人手不足により適切な労務管理がおこなわれていない企業の特徴でもあります。
労働時間が長くなるほど、社員には心身ともに大きな負荷がかかってしまい、離職につながりやすいです。
また、上司が残っているから帰りづらい、残業しないと評価されないという風習が会社にある場合も、必然的に長時間労働を作り出す環境になっています。
特徴(3)教育やフォロー体制が整備されていない
社員に対する教育プログラムやフォロー体制が整備されていないのも、離職率が高い企業の特徴です。
特に、慣れない環境にいる新入社員に対するサポート体制がない場合、新入社員が大きな不安を感じ、離職につながるケースもあります。
また、先輩社員や上司によって指導方法が異なる場合、混乱を招き生産性の低下につながることから、モチベーションや自信が低下してしまい、離職につながる可能性もあります。
離職率の低い企業の特徴とは?
 離職率の低い企業には共通する特徴があります。ここでは主に3つの特徴を紹介します。
離職率の低い企業には共通する特徴があります。ここでは主に3つの特徴を紹介します。
特徴(1)残業が少ない
離職率が低い企業は、残業が少ない傾向にあります。
残業が少ない企業では、ワークライフバランスが取りやすく、仕事とプライベートの両立がしやすいというメリットがあります。プライベートの時間を充実できると精神面でも安定するため、ストレスを抱えにくいのが特徴です。
残業が多い企業では休息が十分に取れず、ストレスを感じて退職してしまうことも。仕事における精神的負担を軽減させるためにも、企業側はできるだけ残業が少なくなるように気をつけましょう。
特徴(2)高収入
給与が高いことも離職率が低い企業の特徴の一つです。働いた対価として給与に反映されることで、従業員のモチベーションの向上につながります。
反対に、給与が低ければ経済面で不安定になり、仕事でも私生活でもストレスを感じてしまい、最悪の場合転職してしまう可能性も。
安定した収入により生活にも心にも余裕ができ、結果としてワークライフバランスの取れた暮らしが送れます。高収入の企業は、離職率を低くする以外にも、入社率の向上にも役立ってくれます。
特徴(3)福利厚生が充実
離職率が低い企業の特徴として、福利厚生の充実も挙げられます。
近年、各種手当や休暇制度、育休・産休制度など整備されている企業は増えていますが、それだけでなく、従業員が利用しやすい環境が用意されていることが大切です。
従業員にとって有益な制度があるにも関わらず、実際に申請するとなるとハードルが高くなかなか利用できないという声も数多くあります。そのような企業では、退職してしまう人も増えてしまいます。
また、特別休暇や各施設の優待割引など従業員のプライベートでの支援も満足度の向上につながり、離職率の低下が期待できます。
福利厚生の整備・充実は、離職率の低下のみならず入社率向上のためにも必要不可欠と言えます。
業界別の離職率の傾向
 2022年に厚生労働省が調査した「令和3年雇用動向調査結果の概況」によると、業界別に開きがあることが見て取れます。業界別の離職率は以下の通りです。
2022年に厚生労働省が調査した「令和3年雇用動向調査結果の概況」によると、業界別に開きがあることが見て取れます。業界別の離職率は以下の通りです。
|
業種
|
離職率(%) |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 10 |
| 建設業 | 9.3 |
| 製造業 | 9.7 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8.7 |
| 情報通信業 | 9.1 |
| 運輸業、郵便業 | 11.5 |
| 卸売業、小売業 | 12.3 |
| 金融業、保険業 | 9.3 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 11.4 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 11.9 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 25.6 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 22.3 |
| 教育、学習支援業 | 15.4 |
| 医療、福祉 | 13.5 |
| 複合サービス事業 | 8.1 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 18.7 |
(参考:厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概況」)
2021年に離職率が最も高かったのは、前年の調査に引き続き「宿泊業、飲食サービス業」、次いで「生活関連サービス業、娯楽業」となっています。
一方、離職率が最も低かったのは「複合サービス事業」でした。
宿泊業、飲食サービス業(25.6%)
「宿泊業、飲食サービス業」は、最も離職率が高い業種となっており、産業別の中でも人材の流動性が高く入職率も高い傾向にあります。
一般消費者を対象とするため、土日祝日も勤務することが多く労働時間が不規則な業界であることも離職率の高い要因の一つと言えます。
生活関連サービス業、娯楽業(22.3%)
「宿泊業、飲食サービス業」に次いで離職率が高かったのが、「生活関連サービス業、娯楽業」でした。
生活関連サービス業とは、美容室や家事サービス、クリーニング店といった個人の生活に関わるサービスを提供する業種のことを指します。
娯楽業とは、映画館や音楽、スポーツ施設などの娯楽を提供する業種を指します。
こちらも、宿泊業、飲食サービス業と同様に一般消費者を対象とする業種であり、人材流動性も高い傾向にあります。そのため、離職率も入職率も高くなっています。
複合サービス事業(8.1%)
離職率の最も低い業種は、「複合サービス事業」でした。複合サービス事業とは、農林水産業や郵便局の協同組合など複数の業種に関わる事業のことです。
規模の大きな企業が属しており、労働環境の整備が不十分な中小・ベンチャー企業が少ないため、離職率が低いと考えられます。
電気・ガス・熱供給・水道業(8.7%)
「電気・ガス・熱供給・水道業」は「複合サービス事業」に次いで離職率の低い業種です。
生活に欠かせないサービスを提供しており、競合も少なく仕事がなくなることもまずありません。そのため業界自体が安定していることが多いため離職率が低い傾向にあります。
企業の離職率が高くなることで想定されるデメリット
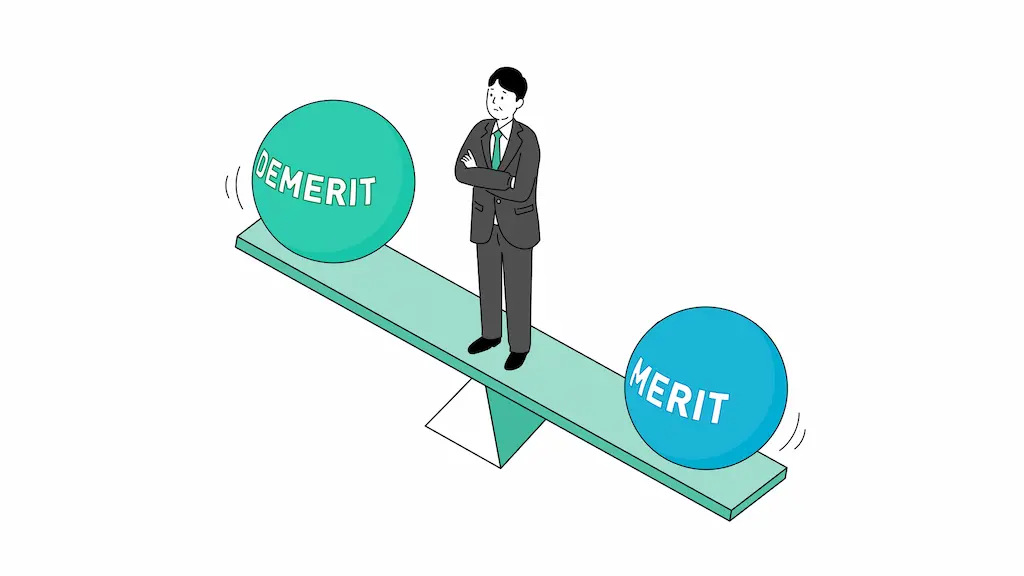 離職率が高くなることで、企業にはどのようなデメリットが生じるのでしょう。想定されるデメリットを紹介します。
離職率が高くなることで、企業にはどのようなデメリットが生じるのでしょう。想定されるデメリットを紹介します。
- 採用・教育コストが無駄になる
- 既存社員の負担が増える
- 企業のイメージダウンにつながる
採用・教育コストが無駄になる
離職率が高い場合、採用や教育にかけたコストが無駄になるというデメリットがあります。採用担当者や教育担当者の工数・人件費も合わせると、大きな損失です。
また、離職者の穴を埋めるために再び採用活動をしなければならないため、さらに採用コストがかかってしまいます。
既存社員の負担が増える
離職率が高くなることで、既存社員の負担が増えるというデメリットも想定されます。
せっかく採用した人材が定着せずに、常に人手不足の状態なので、既存社員の仕事量は増える一方です。
既存社員の負担が増えることで不満が募り、離職の連鎖を招いてしまう可能性もあります。
企業のイメージダウンにつながる
企業の離職率は簡単に調べられる時代です。
求職者はもちろん、関連企業も離職率を閲覧している可能性があるため、離職率が高いと企業のイメージダウンにつながるというデメリットが挙げられます。
数年続けて離職率が高い場合には、特に不信感を抱かせてしまうかもしれません。
離職率を下げるために押さえておきたい改善ポイント
 離職率を下げるためには、具体的にどのようなことをしたらよいのでしょうか。離職率を下げるために押さえておきたい改善ポイントを5つご紹介します。
離職率を下げるためには、具体的にどのようなことをしたらよいのでしょうか。離職率を下げるために押さえておきたい改善ポイントを5つご紹介します。
- 給与や福利厚生の見直し
- 働き方の見直し
- 人事評価制度の改善
- 職場環境の改善
- 継続的な人材育成への取り組み
給与や福利厚生の見直し
離職率を下げるために、給与や福利厚生などの待遇面の改善は大きなポイントです。
長く働く上で、福利厚生も含めた待遇面が十分でないと、離職率が高くなってしまうのは当然といえます。
労働量や成果に対する賃金が正当であるか確認しましょう。業界平均や競合他社と比較して、遜色ない待遇を用意することが、離職率の低下につながります。
また、社員が賃金や待遇に対して不満を持っていないかをヒアリングすることも必要です。企業側と社員側で認識をすり合わせ、互いに納得のいく条件にしましょう。
働き方の見直し
自社の労働時間を見直し働き方に幅を持たせることも、離職率を下げるために効果的です。
労働時間が労働基準法で定められている規定を超えていないか、深夜残業や休日出勤が多くないか、十分な休暇をとれる環境であるかを確認しましょう。
また、フレックスタイム制やテレワークの導入により、働き方に幅を持たせられれば、働きやすい環境になります。多様な働き方を用意しておくことは、ライフスタイルの変化による離職を防止でき、離職率の低下につなげられるのです。
人事評価制度の改善
離職率を改善するために、人事評価制度を改善しましょう。精力的に業務に励んでいる社員であっても、適正な評価を受けられていなければ、モチベーションが低下してしまいます。
あまり成果をあげていない社員と同等の評価をされている場合、人事評価に対して不満を抱え、離職につながる可能性もあります。成果に見合った評価がされ報酬を与えられているか、適正な判断により昇進・昇給できているかを見直すことが必要です。
社員が将来性を感じ長く働くイメージを持つためにも、人事評価制度の改善について、経営陣や管理職で検討しましょう。
職場環境の改善
職場環境への不満も離職につながりやすいため、改善すべきポイントです。
社内コミュニケーションを活性化させ人間関係を良好にする、設備や備品を整えるなどができます。社内の風通しをよくするために、社内SNS等を活用し、上司や他部署の社員を含め積極的な交流を促しましょう。
気軽に相談できる環境ができれば、ハラスメントやセクショナリズム防止といった副次的効果も見込めます。職場の設備や備品に不備があれば、それらを整えることにより、より働きやすい環境に改善可能です。
継続的な人材育成への取り組み
社員が自社でどのようにキャリアアップできるかという道筋を示せれば、離職率を下げる効果が期待できます。
自分の望むキャリアプランを自社で実現することが難しいと感じた場合、転職を検討することもあるでしょう。そのような事態を避けるために、複数のキャリアパスを用意することが重要です。
本人の希望についてもヒアリングし、社内の異動や配置転換、研修の提供などを実施できれば、個人の成長を促せるとともに、離職率も下げられます。
研修制度やワークショップへの参加を奨励する、外部講座の受講費を負担するなど、継続的な人材育成に取り組みましょう。
まとめ
 ここまで、離職率の計算方法から算出する際の注意点、業界別の傾向などを紹介しました。
ここまで、離職率の計算方法から算出する際の注意点、業界別の傾向などを紹介しました。
離職率は、企業の働きやすさや人材の流動性における一つの指標です。人材不足が深刻化する日本社会において、従業員のエンゲージメントを高めて定着してもらうためには、離職率の把握は必要不可欠といえます。
しかし、離職率は法で定められた定義がないため、計算方法によっては目的が曖昧になってしまうので注意が必要です。
この記事を参考に自社の目的に応じて離職率を算出し、社員が働きやすい企業づくりを目指しましょう。
開催中の無料セミナー
人が辞めにくい組織をつくるには【青山学院大学 山本寛教授が解説!】
社員のエンゲージメントを向上させ、
定着させるためのマネジメントのポイントセミナー
開催日時:2024年11月15日(金)13:00-14:00
離職対策のポイントを世代別に解説!
不必要な離職を防ぐ!30分でわかる、社員の定着ポイントセミナー
開催日時:2024年11月6日(水)13:00-13:30
中途採用者の定着・戦力化支援のやり方は?
中途社員のオンボーディングのために必要なポイント解説セミナー
開催日時:2024年11月8日(金)13:00-14:00
おすすめのお役立ち資料
離職防止の他、各分野のお役立ちコラムを公開中
離職防止の知恵袋の他、新卒採用の知恵袋、中途採用の知恵袋、社員研修の知恵袋を運営しています。ぜひ合わせてご覧ください。
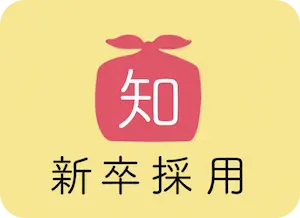 |
 |
 |
 |
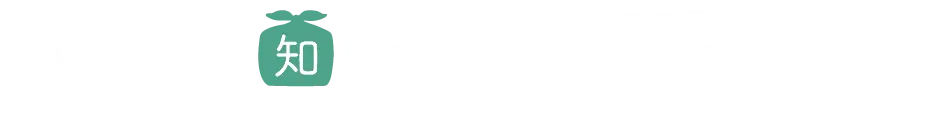
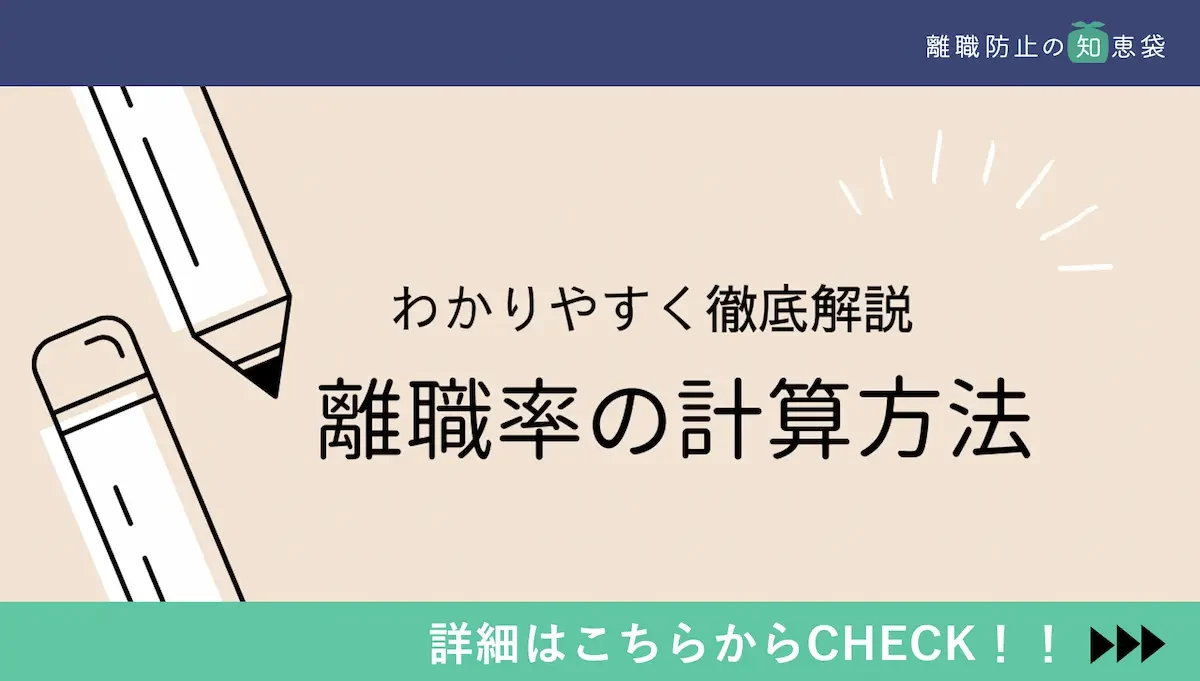
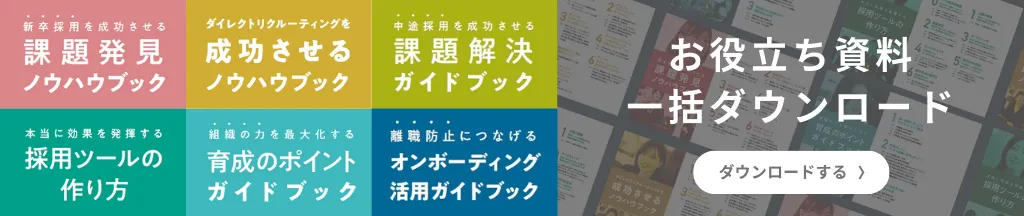
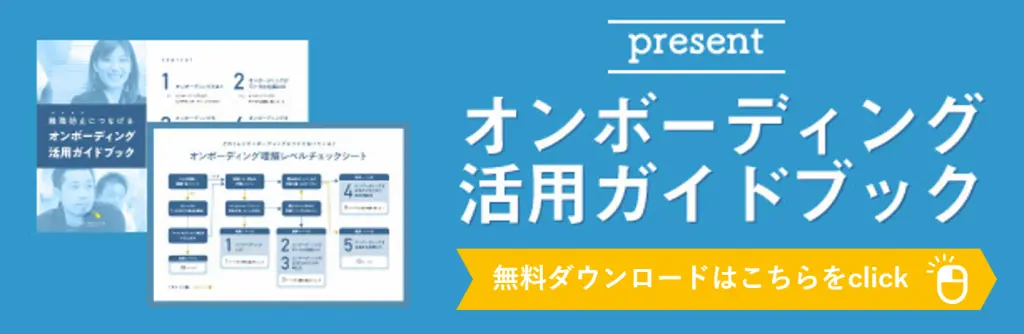
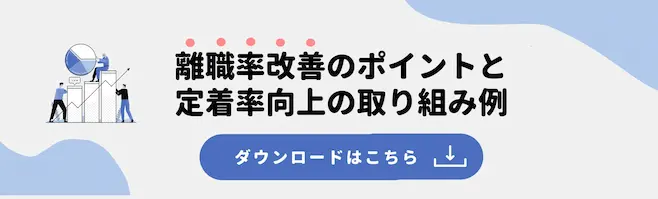
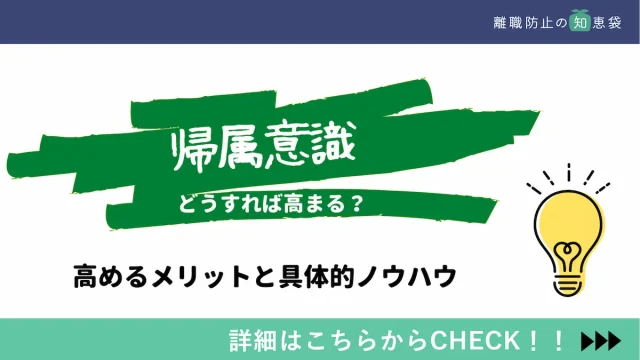
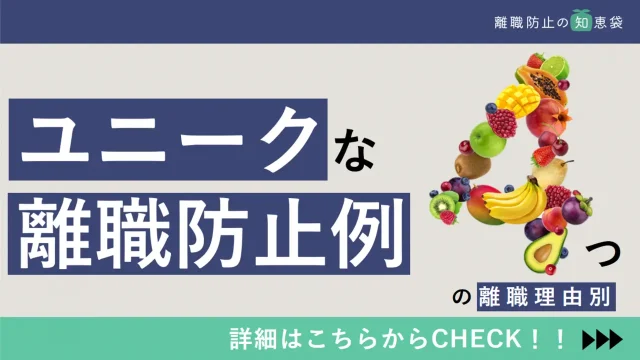
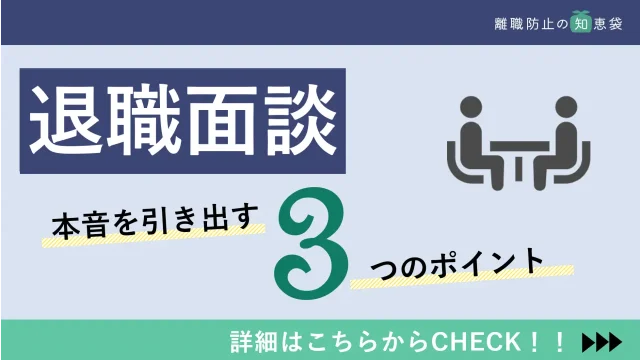
 離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック
離職防止につなげるオンボーディング活用ガイドブック 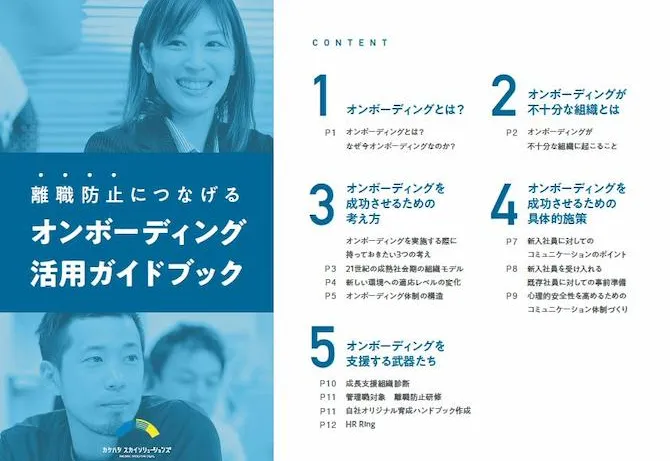
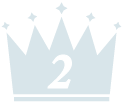 組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック
組織の力を最大化する育成のポイントガイドブック 
 入社2~5年目若手社員意識調査まとめ
入社2~5年目若手社員意識調査まとめ